世界的な環境意識の高まりを背景に、米キャタピラー社では次世代型ハイブリッド機の必要性を確信し、2009年より要素研究をスタート。油圧式と電気式の両方で検証を進めていたが、最終的には効率面も考慮し油圧式で検証を進めることとなった。「競合が電気式ハイブリッドの研究を進めているという情報もありましたし、もちろん環境対応やお客様の燃料消費に対する意識の高まりを感じている一方で、当社としては作業効率を落としてはいけないという意識がありました。CATが初めて市場に送り出すハイブリッド機となるわけですから、とにかくドラスティックな改善、誰もが違いをすぐに実感できるようなものを作らなければならないという思いがあったのです」と本プロジェクトを統括した湯浅は語る。
米本社が油圧コントロールバルブを、そして日本のチームがショベルそのものの機構開発を担当するグローバルチームでテストマシンを準備。元々、ショベルは日本国内におけるニーズが高いうえに競合も多く、切磋琢磨してきたために世界的に見てもレベルの高いノウハウを有している。もちろん、世界中に供給するキャタピラー社のショベルのほとんどが、ここ明石工場で生産されていた。当時、米本社に駐在していた佐々木はこう語る。「テストベッドマシンを作った段階では、コントロールバルブが新しくなったことで操作性が大きく変わってしまった。ショベルを運転する方にとっては、致命的ともいえる大きな問題です。そこで私たちは、操作性と燃費を両立させるべくミッションに向かい、ひたすら調整を繰り返すしかなかったのです」

日米エンジニアの精神が融合して生まれた
画期的なハイブリッド油圧ショベル
-

湯浅 孝之
生産機設計部 部長
Yuasa Takayuki
1988年入社 -

松下 進
実験部 シニアエンジニアリングプロジェクトチームリーダー
Matsushita Susumu
1993年入社 -

佐々木 隆行
機体制御設計部機体制御設計課
Sasaki Takayuki
エンジニアスペシャリスト
2005年入社 -

高橋 一郎
製造部部品工作課工作係 係長
Takahashi Ichiro
2003年入社


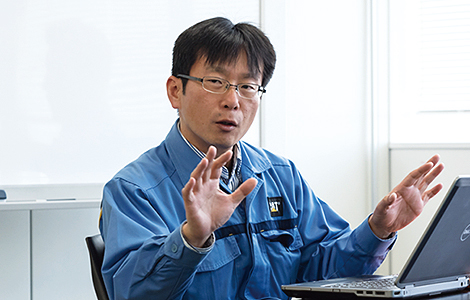
テストベッドマシンを作る段階からチームに加わった松下は、与えられた検証期間の短さに驚きを隠せなかったという。「通常の半分という期間内に必要な検証のすべてを終えなくてはならない。そのためにテストベットマシンを複数台作り、アメリカと日本の2箇所同時に検証を進めていくしかありませんでした。試験条件や結果の共有を、いかに素早く、密に行うのかがポイントとなりました」。操作性のチューニングには相当の時間を要した。数値だけではなく、熟練したオペレーターの感覚を元に調整を行わねばならない。米本社のエンジニアがチューニングを行い、日本人がエヴァリエーターとして評価を行う。英語と日本語の微妙な表現の違いを克服しながら、感覚を指標に置き換えていったのだった。


要素研究を経て、正式に日米合同のプロジェクトチームが発足したのが2011年。グローバルな体制そのものは、CATにおいては珍しいことではない。しかし、与えられたミッションは、これまでにないほど困難なものであった。
「2011年末に話があって、もう翌年明けには生産ラインを立ち上げなくてはならないということになりました。わずか3ヶ月間で、生産設備、生産技術、作業者の指導など、体制を一新しなくてはならなかったのです」と明石工場の製造部門を取り仕切る高橋は振り返る。「急激に市場が変化し、お客様のニーズが高まりを見せていましたし、電気式ハイブリッドで勝負する競合も、急ピッチで開発を進めていました。経営層としては一刻も早くこのプロジェクトを進め、そして必ず成功させなくてはならないという意識があったのです」と湯浅は説明する。
明石工場の敷地内で油圧システムの設計担当は、米本社の基本設計を実際の生産可能なレベルに置き換えることに苦労をしていた。「要求性能を実現するために、理想としてはこういった装置が必要だと。しかし、製造技術的な面やコスト面から検討して、どうしても不可能なものがあります。それを米本社の開発担当者と打ち合わせして、折衷案を探りながら進めていきました」。当然、生産部門との調整も必要になってくる。設計担当と高橋は常に連携を図りながら、互いのミッションを遂行していく。
「2011年末に話があって、もう翌年明けには生産ラインを立ち上げなくてはならないということになりました。わずか3ヶ月間で、生産設備、生産技術、作業者の指導など、体制を一新しなくてはならなかったのです」と明石工場の製造部門を取り仕切る高橋は振り返る。「急激に市場が変化し、お客様のニーズが高まりを見せていましたし、電気式ハイブリッドで勝負する競合も、急ピッチで開発を進めていました。経営層としては一刻も早くこのプロジェクトを進め、そして必ず成功させなくてはならないという意識があったのです」と湯浅は説明する。
明石工場の敷地内で油圧システムの設計担当は、米本社の基本設計を実際の生産可能なレベルに置き換えることに苦労をしていた。「要求性能を実現するために、理想としてはこういった装置が必要だと。しかし、製造技術的な面やコスト面から検討して、どうしても不可能なものがあります。それを米本社の開発担当者と打ち合わせして、折衷案を探りながら進めていきました」。当然、生産部門との調整も必要になってくる。設計担当と高橋は常に連携を図りながら、互いのミッションを遂行していく。

「現行の設備を改造しながら生産ラインの構築を進めていったので、ことあるごとに想定外の問題が持ち上がってきました。その度に設計部門にフィードバックして、問題を解決していきました」という高橋。「設計だけに集中していれば良いわけではありませんでした。米本社にも日本の製造部門にもそれぞれの言い分がある。その橋渡し役としての難しさはありました」と語る。
まったく新しい試みを短期間で進めていかなくてはならず、この先にいったい何が起こるかわからない状況だった。そのため設計も製造も、互いの業務範囲を超え、オーバーラップしながら密に連携を図っていく必要があったのだ。湯浅は「プロジェクトを取りまとめる立場としては、それぞれに権限委譲しつつも、問題が発生したらすぐに現場に行って見極めたうえで、関連部門に働きかける。一緒に考えて対処するというサイクルを回して、クイックに対応していきました」と振り返る。そういったメンバーの苦労は、過去最短の期間で新製品を市場に投入するという、驚くべき結果を生み出したのだった。
まったく新しい試みを短期間で進めていかなくてはならず、この先にいったい何が起こるかわからない状況だった。そのため設計も製造も、互いの業務範囲を超え、オーバーラップしながら密に連携を図っていく必要があったのだ。湯浅は「プロジェクトを取りまとめる立場としては、それぞれに権限委譲しつつも、問題が発生したらすぐに現場に行って見極めたうえで、関連部門に働きかける。一緒に考えて対処するというサイクルを回して、クイックに対応していきました」と振り返る。そういったメンバーの苦労は、過去最短の期間で新製品を市場に投入するという、驚くべき結果を生み出したのだった。



彼らが成し遂げた快挙は、開発期間の短さだけではない。生産性と燃費の両立というコンセプトを、しかもドラスティックなカタチで実現。なによりもユーザーの声が、その狙いが成功したことを物語っていた。市場に与えたインパクトは大きなものとなり、2013年のエジソンアワードをはじめ、日米で各賞を受賞。CAT社内において社長賞という栄誉を付与され、一躍社内でも注目を集めるプロジェクトとなった。もちろん、メンバーそれぞれが個人的に得たものも大きい。
「今までの油圧コントロールバルブとはまったく違った、最先端の技術の深いところが学べたのは大きい。次期のシリーズにも取り入れ、さらに良い製品を作っていきたい」と設計担当は語る。高橋は「今回の経験を通して、柔軟にモノづくりをする意識が芽生えた。どんどん技術は進化していくし、私たち生産部門もそれに対応していく必要があります。そこがまさに設計部隊の横に隣接する明石工場のプライオリティだと思うのです」と述べた。
松下は「誰も妥協せず、目的を共有できたことで、今回の成果が得られたのだと思っています。発売当初は“本当に市場に受け入れられるのだろうか?”という一抹の不安がありましたが、市場の反響やお客様からのフィードバックを見聞きして、今では、私たちがやってきたことが間違いではなかったと確信しています」と振り返る。米本社に駐在し、日米間の技術的な架け橋として奔走した佐々木もこのように語る。「厳しいターゲットであったがため、ミッションを成し遂げた後には、エンジニア同志がより密接な関係になれたような気がします。今後、他のプロジェクトに関わっていくときにも、この共感から生まれた関係は生きていくと思っています」
「今までの油圧コントロールバルブとはまったく違った、最先端の技術の深いところが学べたのは大きい。次期のシリーズにも取り入れ、さらに良い製品を作っていきたい」と設計担当は語る。高橋は「今回の経験を通して、柔軟にモノづくりをする意識が芽生えた。どんどん技術は進化していくし、私たち生産部門もそれに対応していく必要があります。そこがまさに設計部隊の横に隣接する明石工場のプライオリティだと思うのです」と述べた。
松下は「誰も妥協せず、目的を共有できたことで、今回の成果が得られたのだと思っています。発売当初は“本当に市場に受け入れられるのだろうか?”という一抹の不安がありましたが、市場の反響やお客様からのフィードバックを見聞きして、今では、私たちがやってきたことが間違いではなかったと確信しています」と振り返る。米本社に駐在し、日米間の技術的な架け橋として奔走した佐々木もこのように語る。「厳しいターゲットであったがため、ミッションを成し遂げた後には、エンジニア同志がより密接な関係になれたような気がします。今後、他のプロジェクトに関わっていくときにも、この共感から生まれた関係は生きていくと思っています」

そして湯浅が、今回のプロジェクトの成功要因についてこのように分析する。「米国のエンジニアはチャレンジ精神が旺盛で、“こんなことをやってみよう”とワクワクしながら提案してくる。日本人だけでは保守的になりがちですが、向こうには“失敗してもいいからやってみよう”と。前向きな姿勢を受け入れる風土があるのですね。しかし、それだけではきっと破たんしてしまう。そこから先は日本のモノづくりの強さ、ひたむきさ、蓄積してきたノウハウなどが必要になる。それぞれの良いところが最終的に結実した結果だと思っています」。
日本的な精神と米国的精神の融合。真のグローバル企業のあるべき姿を見出すことができた、大変意義あるプロジェクトであったことは間違いない。
日本的な精神と米国的精神の融合。真のグローバル企業のあるべき姿を見出すことができた、大変意義あるプロジェクトであったことは間違いない。
